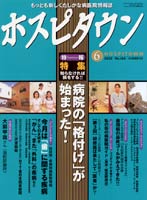
The Doctorsが迫る!
File 03 肺 が ん
ホスピタウン 2002年6月号
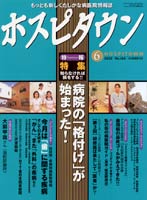 |
The Doctorsが迫る! File 03 肺 が ん ホスピタウン 2002年6月号 |
| 肺がんは早期発見が難しく転移しやすい 肺がんと喫煙率には、密接な関係があります。喫煙者は非喫煙者と比べて、肺がんでの死亡率は男性で4.45倍、女性で2.34倍に上り、さらにー日25本以上タバコを吸う人は肺がんで7倍、喉頭がんでは90倍ものリスクがあります。周囲の人が吸うタバコの煙による「受動喫煙」も大きな問題で、夫がタバコを吸うと、妻が肺がんになるリスクは2倍になると言われています。 現在、肺がんによる死亡者数は年間5万人を超え、1947年の10倍になっています。肺がんは発生率では、男性2位、女性5位ですが、死亡率では男性1位・女性3位に上ります。その理由は3つあります。第1には早期発見がしにくいこと、第2には肺が常時活動している臓器であるために血流量が多く、早期に転移しやすいこと、第3には種類が複雑で治療の効きが悪いということです。 肺がんには、大きく分けると腺がん(50%)、扁平上皮がん(30%)、小細胞がん(10〜15%)、大細胞がん(5〜10%)の4種類があり、また、がんの進行度によって、治療法の選択肢は変わります。治療法は手術療法、化学療法、放射線療法、免疫療法、光線力学的(レーザー)療法、温熱療法などがあります。早い時期の肺がんでは、まず病巣を切除し、その後化学療法や免疫療法によって、細胞単位で転移している可能性のあるがんの治療を行います。免疫療法というのは、注射や薬を使ってからだの免疫力を上げる療法です。早期肺がんなら、80%が治癒します。 しかし、肺がん全体で切除できるのは50%程度です。残りの50%は肺、脳、骨や多くのリンパ節に転移していたり、原発巣が心臓や大血管まで浸潤していて、手術してもあまり意味がないため、第一選択が化学療法や放射線療法になります。小細胞がんは非常に進行の早いがんですが、化学療法がとても有効です。進行がんの場合は、完治率は低くなります。 最近はフィルター付きタバコがほとんどですが、かえって粒子が細かくなり、肺の奥まで強く吸い込んでしまうため、肺の腺がんが増えていると言われています。フィルターが付いているからといって、安全とは言えません。またニコチン、タールは唾液と一緒に飲み込むので、食道がんや胃がんのリスクファクターにもなります。その上、長年の喫煙によって肺胞壁が壊れ、高齢になればほとんどの喫煙者が肺気腫になってしまいます。このように多くの病気のリスクファクターとなるタバコは、すぐにでも止めるのが賢明です。 歴史と、伝統の息づく温かな雰囲気 杏雲堂病院は明治14年創設。私立病院としてはもっとも歴史が古く、併設の佐々木研究所では、結核・がんなどの疾病に大きな研究成果を上げてきました。 呼吸器科には内科、外科両方のスタッフがそろい、科の垣根がありません。検査で異常が見つかったら、手術・化学療法などいろいろな選択肢を説明して、患者さんと一緒にどの治療法がよいのかを考えていきます。リニアックなど大学病院並みの設備があり、レーザーを照射する光線力学的治療や放射線科と連携して放射線治療もすべて行えます。「肺がんの手術をした後、再発を防ぐためにいいと思う方法は、ベータカロチンでも漢方薬でもなんでも勧めるんですよ。私にとって患者さんは、一緒に病気と戦う戦友。一生の付き合いだと思っています」とおっしゃる林先生の人柄を反映して、杏雲堂病院には、親身で温かな空気が流れています。肺がん以外にも、肺気腫、肺炎、気管支炎、ぜんそく、気胸など幅広い疾患を受け入れています。 また、禁煙したい人にはニコチンの禁断症状を和らげる方法として、ニコチン置換療法を実施。ガムを噛む方法と、ニコチンがついた透明なフィルムを体に貼る方法があり、吸収するニコチンの量をだんだん減らして、8週間続けます。貼り薬による方法は大変好評で、禁煙成功率は90%以上です。 予防と検査の方法について 肺がんの予防は、どうすればいいのでしょうか。また、肺がんの検査は、どんな検査を受ければいいのですか? タバコをやめることが一番です! 肺がんの予防法は、なんといってもタバコをやめること!「喫煙指数= 1日吸うタバコの本数×吸った年数」で計算し、喫煙指数が400以上の人は肺がんのハイリスク・グループに入ります。その他には、お酒はほどほどに、ストレスを溜め込まない、ベ一タカロチン・ビタミンC・Eなどの抗酸化作用のある食物を多く摂取して、バランスのよい食生活に気をつけることです。 また、肺がんの検査は5種類あります。 (1) 胸部レントゲン写真 (2) たんの検査 容器にたんを3日間ため、がん細胞がいるかどうかを調べる。 (3) 胸部CT検査 (4) 気管支鏡検査 異常が見つかった場合に、病気を確定するための検査。局所麻酔や静脈麻酔をかけて5mmくらいの太さの気管支鏡を喉か鼻から入れ、肺の中の病巣から組織や細胞をとり、病理検査を行う。軽く眠った状態なので、苦しさはほとんど感じない。 (5) CTガイド下針生検 画面に映らない小さな影の場合には、CTで見ながら胸壁から細い針を刺し、病巣から組織や細胞をとって、病理検査を行う。胸部レントゲン写真だけでは肋骨や臓器に隠れたがんは発見しにくいので、40歳以上でタバコを吸う人は、たんの検査と胸部CTの検査も受けるとよいでしょう。また、2週間以上継続してせきやたんが続いたり、血たんが出るようなら、必ず呼吸器科のある病院で検査を受けましょう。 ・Personal Data 林永信(はやし・ながのぶ) 1972年東京医科大学卒業。肺がん治療の草分け的存在であった同大学附属病院外科第一講座に入局し、多くの症例を手がける。1985年南カリフォルニア大学医学部ロサンゼルス小児病院に、悪性腫瘍のレーザー治療研究のため留学。東京医科大学講師を経て1990年より東京医大派遣助教授、杏雲堂病院呼吸器科部長。1997年副院長に就任。「肺がんの診断手順と治療方針」、「早期肺がん」など多数の著作・論文を発表。日本呼吸器外科学会評議員・専門医。日本呼吸器学会指導医・専門医。 |