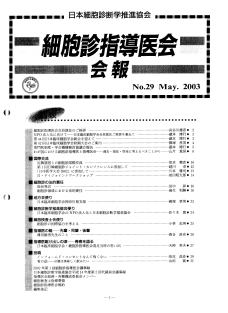
細胞診指導医会 会報
№29 May.2003
日本細胞診断学推進協会
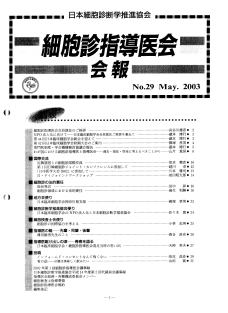 |
細胞診指導医会 会報 №29 May.2003 日本細胞診断学推進協会 |
| 指導医駆け出しの頃-青春を語る |
| 日本臨床細胞学会・細胞診指導医会発足当時の思い出 |
| 日本臨床細胞学会名誉会員 日本細胞診断学推進協会理事 天神 美夫 佐々木研究所付属杏雲堂病院名誉院長 |
|
日本の細胞診断学は昭和35年(1961)に日本婦人科細胞診談話会として始まり,すぐに日本臨床婦人科細胞学会となり,医療全領域をカバーする現在の日本臨床細胞学会に発展してきた。学会発足当時から米国の細胞診システムを念頭に置いた形式が考えられていた。そのためには,アメリカのcytologistに当たる細胞診の専門医の必要性が叫ばれていた。 当時のアメリカは勿論のことヨーロッパでも病理診断学から発展してきた経緯もあり,病理医の中から細胞診専門医が生まれてきている。したがって,細胞形態の特徴をとらえる表現が多い,病理標本上の細胞所見との対比に主限をおいている。病理標本は顛微鏡下でみると組織の側面を観察する機会が多い,細胞珍材料は細胞そのものの表面を観察することになるため,血液標本的なイメージとなる。 学会発足当時の日本での病理学者は,細胞診に対する認識は低く興味を持つ研究者は少なかったようである。太田邦夫先生(当時癌研,病理部長)のような著名な病理学者もおられたが,アメリカでの臨床検査システムの中で研究された方以外は臨床診断との対比の上で患者の正確な病状把握するというような環境でなかった。特に,がんの早期診断の上でその現象が目立っていた。臨床診断は臨床の問題,病理診断は病理の範疇と分離していた,ここで私個人のエピソードを紹介する。 子宮頸部がんのレベルでは,早期の第Ⅰ期がんの前に当たるがんやさらにその前駆として前がん状態の時期があるのではないかとの議論が世界的に婦人科レベルでは起こってきていたため,米国・ヨーロッパ・グループで会議を開き浸潤まえのがんをca.in situ(上皮内がん,第0期がん)と表現することになり,その研究が臨床レベルで盛んに行われていた。 特に,頸部がんの治療法の選択に役立つためである。コルポスコピーの発達がこれに拍車をかけることになる。コルポでの20倍レベルでの所見で子宮頸部の異常所見の状態は,かなりのことがわかり始めたことにもよる。 当時,私は癌研の婦人科にいたある日,外来患者の細胞診で異常な細胞をみつけた。従来の頸がん細胞のような面付きではなく核内構造には異常が少なく核は大きくいわゆるN/C比が大きい異常細胞である。これが臨床的な最初の決め手となって上皮内癌と診断できた。 増淵一正先生(当時癌研婦人科部長)に相談すると先生は大変喜び,これこそ0期がんの細胞に違いないということになり,学会で発表することになった。 そして日本癌学会で発表することになり,準備を始める。現在の癌学会は大きくなり会員数も増加しているが,その当時は会員も少なく会場は東大の講堂であった。 私は内心得意であった,なにしろ日本で最初の細胞診による上皮内がん症例の報告である。細胞の写真を示しこれが上皮内癌細胞と考えてよいとした。 ところがである,200人ばかりの会場から一斉に20人くらいの手が挙がった。よく見ると当代一流の病理学者や大学の病理教授の先生方である。これは大変なことが起こる.「上皮内癌を癌であると認めた訳ではない」「病理学的には細胞1個で癌と診断するわけではない」「細胞の組織構築や側方浸潤,基底膜との関係はどうなっているか」「細胞1個や2個で癌と診断するのは無謀である」等々,質問が山のごとく殺到した。 私はろくに返答できずただおろおろとするばかり,冷や汗が頭のてっペんから足にかけて流れ落ちる。座長も困って会場を見渡すばかり,私も演壇から降りることもできず棒立ちのまま,発表のやり方がまずかったかと反省しきり。 その時,吉田富三先生(当時,東大病理学教授)がやおら手を挙げた。また叱られるかなと思っていると「こんな若い研究者が真剣になって調べていることだから,何年かたって振り返ると癌細胞と認識できる可能性もないとはいえない。現在の病理学の常識とはかけ離れているが,長い目で見てやろうではないか」と言われた。やっと壇上から降りられた。 吉田先生には大変感謝している。吉田先生に報いるためにも上皮内癌の細胞所見の解明に情熱を注ぐことになる.28歳当時の苦い思い出である。 また,一見ありえないような研究内容でも実験基盤がしっかりしていれば長期的にみる必用があることも悟った。これは,大きな人生の指針にもなった。 臨床医は一日でも早くがんを診断し一人でも多く治すこと ができればとの思いが細胞診に打ち込むことになる。これがアメリカと違う方向の発展形式をたどる事になった。 細胞診を発展させるためには,細胞診を専門とする医師や細胞診のよくわかる臨床検査技師を必用とする。米国のようなシステムを作らなければ日常の臨床検査の中には組み込めない,Cytologistとcytotechnologistによるチーム診断システムが必要となるが日本ではそのような慣習は全くなかった。 そこで35歳前後の急進的な仲間が集まって議論に入った。大学でいえば講師クラスの人たちばかりであることもあって,議論はかみ合わない。いっペんにその制度に持ち込むには無理がある,まずアクティブメンバーを作って俸い先生方を口説くことから姑めようとなり活動を開始した。その当時の学会理事はほとんど臨床系大学教授であった。 メンバーはまず自分の教室の教授にこの制度の必要性を説いたが,反応は極めてよくない。一般的な答えは君が専門医になると教授の上に立つ事になるのかとの危惧があり,うちの教室では必要ないとの返答になる。そこでA大学の講師はB大学の先生を口説く,Cメンバーはほかのがんセンターのボスに説明するというような戦略に変え,臨床検査技師教育が主な仕事である旨の理解を得ることができるようになった。臨床系の教授がはるかに大きな権限とカを持っていた時代のことである。 次に問題になったのは,ネーミングである。「細胞診専門医」の名称に人気があった。しかしこれだと誤解を招く恐れがあることから,仕事の内容をよくあらわす「細胞診指導医」のほうがよいとの方向でまとまった。麻酔科が指導医の名称で仕事を開始しており,名前が定着していたのを参考にした。 次は,細胞診業務の内容である。病理系の先生はジェネラル細胞診こそ専門医の仕事であることを強調する,臨床系のメンバーは他の領域の細胞は診断できないのだから臓器別とする意見が出され,紛糾したが臨床系のメンバーが多いせいもあって現在の形となった。 臓器別名称は頭につけず「細胞診指導医」とした。これも将来の変化に対応しやすい事を念頭に置いたためでもある。しかし,その結果2つの傾向がめだった,がんの診断に携わっている若手の医師が学会に多数参加してきたが,病理系の医師の増加率は少なかった。ネーミングとは難しいものである。 次は最初の指導医メンバー選出の問題である。基準は無い,学会に演題を出している医師でよいとの意見やそれでは実力を示したことにならないなどの意見が多く出され,結局,学会の会場でテストを行い実力のあるところを示し会員に認めてもらう方式がよいとなった。これが現在行われている「スライドカンフアレンス」のはしりである。 当然私にも順番が回ってきた,確か5例の細胞診標本のスライド写真が出たように思う。会場の諸君の目が一斉にこちらに降り注ぐ。間違えたら満座の中で恥をかく,久しぶりに緊張が走る。 全開正解であった。典型的な症例であったためでもある。 試験が終わって後ろを振り返ると,よかったねと微笑む目や,旨くやったなと冷たく見つめる顔があった。とにかく私はホッとした。 昭和43年1月に細胞診指導医制度と細胞検査士制度が制定され,昭和43年11月に指導医65名,昭和44年3月に細胞検査士8名が誕生した。 当時の学会長福田 保先生,増淵一正先生,水野潤二先生の後擾に深く感謝するものである。 最近の細胞診専門医の問題と課題 最近の医療を取り巻く情勢は大きく変化しつつある。患者が病院,医療機関を選ぶ時代となってきた,それはむしろ当然の事でもあるといえる。 患者が自分の病気を治してくれる最も信頼できる病院に行くことになる。最近までは知人,友人同士のロコミで医療機関の内容や診療する医師の評判を調べ病院を選択しているのが一般的であったが,ここ2,3年で選択方法が変わってきた。インターネットが普及してきたため,自分自身や家族が病院のホームページから病院の専門性や臨床医の特徴をつかもうとする,ある所の調査では約5割の人がこれを利用しているとの報告もある。都会ではこの傾向が強い。そうなると病院もホームページを重要視せざるを得ない。 病院の規模や設備内容,患者さんに対するサービスは勿論のこと,医師のレベルを表示したくなる。そこで専門医が重要な課題となった。 各学会が指導医とか,専門医を名乗るのは勝手だが,厚生労働省が認めた専門医ではない。厚生労働大臣が認めるための条件をクリアし専門医の承認を受けた学会は現在のところ麻酔科,産婦人科等8学会がある。 その条件の中に学会は法人格を持つ必要があり,法人格には公益法人(財団,社団法人)中間法人,NPO法人等がある。また政府内では,公益法人法の改正が議論され間もなくその大綱が示されることになった。公益法人は従来,関係省庁の認可制であったものが,届出制に変わる方向にある。 日本臨床細胞学会は現時点でNPO法人化を進めているようである。 しかし学会とは学問の進歩発展に寄与する場所を提供することが本来の目的であるべきものである。制度そのものも大切だが、学会機関誌や学術集会に発表される研究内容がより重要となる。最近の細胞学の進歩は目覚しいものがあり,遺伝子,染色体,たんばく質等の研究の内容は月レベルで変わってきているといっても過言ではない。これらの新しい事実を形態学の一種である細胞診断学にマッチングさせ,診断効率をさらに高める研究を進めることは現在の本学会の大きな使命の一つでもある。症例の検討も重要だが,細胞内の最近の情報を細胞診上の細胞所見にフイードバックする研究はより重要となる。 新しい研究テーマに基づいた論文や講演が多数発表されることを期待してやまない。学会が会員と共にさらなる発展をとげることを祈るものである。 |
| 2003年3月末 |